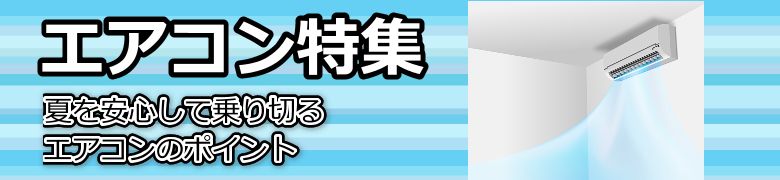ドラムを始めたいけれど、何から手をつけて良いか分からない。
そんな初心者の方に向けた記事です。
勢いでドラムセットを買ってしまい、後から失敗したと感じる人も少なくありません。
このブログでは、購入前に知っておきたいポイントや、後悔しないための準備方法を分かりやすく紹介しています。
経験がなくても安心して読める内容です。
想定外の音と振動問題
自宅でドラムを始める時、最も直面するのが騒音問題です。
ドラムは叩いた時の音だけでなく、振動も発生させます。
これは多くの初心者が予想以上に苦労するポイントとなっています。
アコースティックドラムの場合
アコースティックドラムの場合、その音量は一般家庭ではコントロールが難しいレベルです。
壁や床を通じて振動が伝わり、近隣住民とのトラブルになるケースも少なくありません。
特に集合住宅では、防音対策なしでの演奏はほぼ不可能と考えた方がいいでしょう。
電子ドラムの現実
電子ドラムなら大丈夫と思われがちですが、実際にはそうとも限りません。
確かに音量調整は可能ですが、パッドを叩く打撃音や、特にバスドラムペダルの振動は思いのほか響きます。
インターネット上には電子ドラムを買ったのに夜は使えないという声が多数見られます。
防音対策の課題
防音対策には様々な方法がありますが、効果的な対策をするためには追加費用がかかります。
防音マットや遮音パネルを導入しても、期待したほどの効果が得られず、さらなる投資が必要になることも。
結果として、買ったはいいが、思うように練習できないというジレンマに陥る方が多いのです。
| 住居タイプ | アコースティックドラム | 電子ドラム |
|---|---|---|
| 一戸建て | 防音室が必要 | 防振・防音マット推奨 |
| マンション | 実質的に困難 | 時間帯制限と防振対策必須 |
| アパート | ほぼ不可能 | 隣人への配慮が必須 |
意外と狭い設置スペースの現実
ドラムセットのカタログやウェブサイトの写真では、広々としたスタジオに置かれた姿が映っていることが多いですが、実際に家庭に置くとなると話は別です。
初心者がよく直面する問題が、思ったより場所を取るという現実です。
アコースティックドラムの場合
アコースティックドラムのフルセットでは、直径約2メートルの円形スペースが最低限必要になります。
これは一般的な6畳間の約半分のスペースを占めることになります。
さらに、演奏時にはスティックを振るスペースも考慮すると、実際には3畳程度は必要と考えた方がいいでしょう。
電子ドラムの場合
電子ドラムは比較的コンパクトですが、それでも畳1.5枚分ほどのスペースは確保する必要があります。
折りたたみ式でない限り、使わない時も常に同じスペースを専有することになります。
これにより、部屋の使い勝手が悪くなり、生活に支障をきたすことも少なくありません。
生活への影響
一度組み立てると解体が面倒なため、やっぱり場所を変えたいと思っても簡単には移動できません。
特に学生や賃貸住宅に住む方は、引っ越しの際の運搬や保管方法まで考慮する必要があります。
事前対策のすすめ
思っていたより大きかったという後悔を避けるためには、購入前に設置予定の場所に実際のサイズを図って確認することをおすすめします。
生活動線を妨げないか、他の家具との兼ね合いはどうかなど、具体的にイメージしておくことが重要になります。
予想を超える隠れた費用の実態
ドラムセット本体の価格だけを見て購入を決めると、後から思わぬ出費に驚くことになります。
初心者が見落としがちな隠れた費用について理解しましょう。
必要な付属品
基本的な付属品として、ドラムスティック、ドラムスローン(椅子)、フットペダル、ヘッドホンなどが必要となります。
これらは本体とセットになっていないことが多く、別途購入すると数万円の追加費用がかかります。
防音・防振対策費
特に重要なのが防音・防振対策費です。
最低限の防振マットでも1万円前後、本格的な防音対策を行うとなると数十万円かかることもあります。
これらは初期見積もりには含まれていないことがほとんどです。
| 項目 | 概算費用 |
|---|---|
| 基本セット | 5〜30万円 |
| 付属品(スティック、椅子など) | 1〜5万円 |
| 防音・防振グッズ | 1〜5万円 |
| 本格防音室 | 30〜100万円 |
| メンテナンス費(年間) | 5千〜2万円 |
維持費と修理費
購入後の維持費も考慮したいポイントです。
アコースティックドラムではヘッドの交換やチューニング用具、電子ドラムでも故障時の修理費用や部品交換費が発生します。
特に安価な初心者向けモデルは耐久性に問題があることも多く、結果的に安物買いの銭失いになりかねません。
中古品の落とし穴
中古品を選ぶ場合も注意が必要となります。
一見安く見えても、使用状態によっては修理やパーツ交換が必要になり、結果的に新品を買うより高くつくケースもあります。
初期費用と維持費を含めた総コストを見積もっておくことで、後悔を避けることができるでしょう。
モチベーション維持の難しさ
カッコよくドラムを叩きたいという憧れだけで始めても、継続することは意外と難しいものです。
初心者がぶつかる大きな壁の一つが、モチベーション維持の問題です。
上達の遅さ
最初のうちは新鮮さから熱心に練習できても、上達には時間がかかります。
基本的なリズムキープや両手両足の独立した動きを習得するだけでも数ヶ月を要することがあり、思うように演奏できないもどかしさから挫折してしまう人も少なくありません。
生活リズムとの両立
生活リズムとの兼ね合いも課題です。
仕事や学校で疲れた後に練習する気力を保つのは難しく、特に音を気にする環境では今日は遅いから練習は控えようという判断になりがちです。
気づけば週に1回も触れていない状態になり、徐々に上達が止まります。
放置されるドラムセット
SNSではドラムセットを買ったけど、もう何ヶ月も叩いてないという投稿が珍しくありません。
これは単なる怠慢ではなく、継続するための環境や目標設定が整っていないことが原因であることが多いのです。
継続のための戦略
継続のコツは、小さな成功体験を積み重ねることです。
難しい曲に挑戦するよりも、簡単な曲を完璧に叩けるようになることから始め、徐々にレベルアップしていく方法が効果的です。
また、定期的にレッスンを受けることで、他者からのフィードバックやアドバイスを得られ、独学では気づかない改善点も見つかります。
セット選びの失敗と対策
ドラムセットを選ぶ際、初心者が陥りやすい失敗には特徴的なパターンがあります。
これらを理解しておくことで、自分に合った適切な選択ができるようになります。
価格だけで選ぶリスク
安さだけを基準にすると、演奏性や耐久性に問題があるモデルを選んでしまう可能性があります。
特に電子ドラムの場合、安価なモデルでは打感が不自然だったり、音源の種類が限られていたりします。
これがストレスとなり、練習意欲を削いでしまうことも。
自分のスタイルに合わないセット
ジャズを演奏したいのにロック向けの大きなセットを買ったり、逆にパワフルな演奏をしたいのに小さめのコンパクトセットを選んだりすると、後々ミスマッチを感じることになります。
自分がどんな音楽を演奏したいのかを明確にしてから選ぶことが大切になります。
拡張性を考慮していない
初心者のうちは基本的なセットで十分でも、上達するにつれて追加のシンバルやタムを欲しくなるものです。
初めから拡張性の高いモデルを選んでおかないと、後から全て買い換えないといけないという状況になりかねません。
試奏せずに購入する
ネットショッピングの普及で、実際に触れることなく購入するケースが増えています。
しかし、ドラムは非常に身体性の高い楽器であり、フィーリングや音色は実際に叩いてみないとわかりません。
できる限り店舗で試奏するか、レンタルなどで体験してから決めることをおすすめします。
選び方のポイント
選び方のポイントとしては、まず自分の演奏スタイルや好みのジャンルを明確にすること。
次に、生活環境に合わせた音量調整可能なモデルを検討すること。
そして、初心者でも扱いやすい標準的な配置のセットから始めることが賢明です。
高額な買い物だからこそ、焦らずじっくりと情報収集を行い、納得のいく選択をしましょう。
種類別の後悔と対策:アコースティックvs電子
ドラムセットには大きく分けてアコースティックと電子の2種類があります。
それぞれに特有の魅力と課題があり、選択を誤ると後悔することになります。
両者の特徴を比較し、自分に合った選択をするための参考にしてください。
アコースティックドラムの後悔ポイント
アコースティックドラムは、生の音と振動が魅力ですが、それが同時に最大の課題となります。
購入後によく聞かれる後悔の声には次のようなものがあります。
- 騒音問題: 音量が非常に大きく、一般住宅では近隣とのトラブルになりやすい
- 設置場所: フルセットは予想以上にスペースを取り、部屋が狭くなる
- メンテナンス: ヘッドの交換やチューニングなど、定期的な手入れが必要
- 湿度管理: 高湿度環境ではサビやカビの原因になる
対策としては、防音室の設置を検討するか、練習用のサイレントヘッドやローボリュームシンバルを導入する方法があります。
また、スタジオを定期的に利用するという選択肢も検討する価値があります。
電子ドラムの後悔ポイント
電子ドラムはヘッドホン練習ができる利便性がありますが、購入後に不満を感じる点もあります。
- 打感の違和感: 本物のドラムとは異なる反発感や硬さを感じることがある
- 表現力の限界: 特に安価なモデルでは、繊細なタッチやテクニックが表現しにくい
- 音源の質: 内蔵音源に飽きてしまい、外部音源が必要になることも
- 故障リスク: 電子機器なので、センサーやケーブルのトラブルが発生することがある
対策としては、メッシュヘッド採用モデルを選んで打感を向上させる、USBでPCと接続して音源を拡張できるモデルを選ぶなどの方法があります。
選択のポイント
どちらを選ぶのが良いのかは、住環境と予算、そして目的によって変わります。
下記の表を参考に、自分に合ったタイプを検討してみてください。
| 条件 | おすすめのタイプ |
|---|---|
| マンション・アパート住まい | 電子ドラム |
| 防音設備がある | アコースティック |
| 予算が限られている | 中級電子ドラムかコンパクトなアコースティック |
| バンド活動が目的 | アコースティック(+スタジオ練習) |
| 自宅練習が中心 | 電子ドラム |
購入前にできる体験方法
ドラムセットは大きな買い物です。
購入して後悔しないためには、事前に体験できる方法を活用することをおすすめします。
ここでは、初期投資を抑えながらドラム演奏を試せる方法をご紹介させて頂きます。
練習パッドから始める
まずは練習パッドという、ドラムスティックの操作や基本的なリズム感を養うための道具から始めるのが賢明です。
練習パッドのメリットは以下の通りです。
- 価格が手頃(1,000円〜10,000円程度)
- 静かで場所を取らない
- 基本的なスティックコントロールが学べる
- いつでも気軽に練習できる
練習パッドでまずはリズム感やスティックコントロールを身につけることで、ドラムが自分に向いているかを低コストで判断できます。
基礎練習用のアプリと併用すれば、効率よく上達することも可能です。
スタジオ体験の活用
実際のドラムセットに触れる機会として、音楽スタジオの利用がおすすめです。
多くのスタジオではドラムセットが常設されており、時間単位で利用できます。
- 1時間あたり1,000円〜3,000円程度で本格的なセットが使える
- 音量を気にせず思いきり演奏できる
- 様々なタイプやメーカーのドラムに触れられる場合もある
- 録音設備があれば自分の演奏を客観的に聴ける
まずは月に数回スタジオを利用して練習し、継続できそうか、本当に自宅に欲しいと思えるかを見極めることで、衝動買いによる後悔を避けられます。
楽器店でのトライアル
多くの楽器店では試奏コーナーが設けられています。
特に大型店舗では電子ドラムの展示も充実しており、実際に触れて音や打感を確かめることができます。
- 複数のメーカーやモデルを比較できる
- 店員からアドバイスが得られる
- 付属品や防音グッズも同時に相談できる
試奏だけでは短時間ですが、叩いた感じや音の違いを体感することで、イメージと現実のギャップを埋めることができます。
実際に手に取って確かめることで、失敗のリスクを大幅に減らせるでしょう。
自宅練習環境の整え方
ドラムを上達させるには、継続的な練習が大切になります。
そのためには、快適に練習できる環境を整えることが重要になります。
ここでは、自宅での効果的な練習環境づくりのポイントをご紹介させて頂きます。
防音・防振対策の基本
ドラム練習の最大の障壁となるのが音と振動です。
効果的な対策を施すことで、近隣とのトラブルを避けながら練習を続けることができます。
- 防振マット: バスドラムやドラムスローンの下に敷くことで、床への振動伝達を軽減できます。
専用品でなくても、厚手のヨガマットなどで代用することも可能です
- 防音パネル: 壁に取り付けることで、音の反射や漏れを抑えられます。
費用をかけずに始めるなら、厚手のカーテンや毛布などを壁に掛けるだけでも多少の効果があります
- ラバーマット: 電子ドラムのペダル部分の下に敷くことで、踏み込み音を軽減できます
- 時間帯の配慮: どんな対策をしても完全な防音は難しいため、近隣の生活時間を考慮した練習時間設定も重要です
快適なレイアウト作り
限られたスペースでも効率よく練習できるよう、工夫されたレイアウトを考えましょう。
- 動線確保: ドラムセットへのアクセスが簡単な配置にすることで、セッティングが面倒で練習しないという事態を避けられます
- 高さ調整: ドラムスローンやシンバル、タムの高さを自分の体格に合わせて調整すると、疲れにくく長時間練習できます
- 視界の確保: 譜面台やメトロノーム、スマートフォンなどを見やすい位置に置くことで、練習効率が上がります
- 収納スペース: スティックや教則本、チューニングキーなどの小物を整理する場所を確保しておくと、練習の度に探し回る手間が省けます
モチベーション維持のための工夫
継続的な練習のためには、モチベーションを保つ環境づくりも大切になります。
- 録音・録画機能: 自分の演奏を記録して客観的に聴くことで、上達を実感できます。
スマートフォンでも簡単に録音できるので活用しましょう
- 練習記録: カレンダーやアプリで練習時間や内容を記録すると、成長の過程が可視化されモチベーションにつながります
- 目標設定: 〇〇の曲を1ヶ月以内に演奏できるようにするなど、目標を設定することで、練習に目的ができます
- オンラインコミュニティ: SNSやドラム専用掲示板などで同じ趣味の人とつながると、情報交換や励まし合いができます
適切な環境を整えることで、ドラム練習は継続しやすくなります。
最初から完璧な環境を求めるのではなく、できることから少しずつ改善していく姿勢が大切になります。
まとめ
ドラムを始めるのは素晴らしい挑戦ですが、事前の準備や情報収集が不足していると、騒音、スペース、費用、モチベーションなど、様々な壁にぶつかり後悔につながりかねません。
大切なのは、ご自身の住環境や予算、そして「なぜドラムを叩きたいのか」という目的を明確にすることです。
衝動買いを避け、練習パッドや音楽スタジオ、楽器店での試奏など、購入前に必ず体験する機会を持ちましょう。